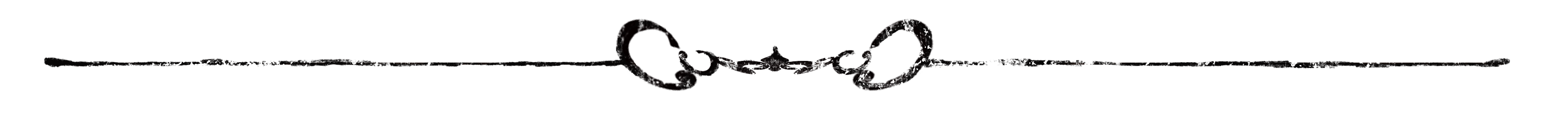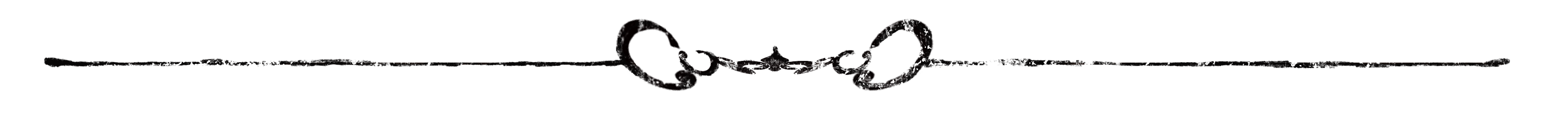新しく荘園へとやってくる人物が囚人であった男と聞いた者達の反応は様々だった。
恐ろしい男だったらどうしようかという不安、役に立てばそれでいいという無関心、どんな人間であれ仲間になるのだから親しくなりたいという希望、捕まる前は発明家であったと聞いて好奇心に溢れている者もいた。そんな中で僕の立ち位置と言えば限りなく無関心に近かったと思う。
けれどその無関心の中に僕が欲していたものを一度は手に入れ、そしてそれら全てを失った人間に対する憐憫が混ざっていたのだから自分で言うのもなんだけれど酷い奴だなと少しだけ自分が嫌になった。
さて、元囚人であった彼、ルカ・バルサーが荘園に訪れる日はあっさりとやってきた。皆で仲良くお出迎えなんてすることはなく僕は朝からゲームに参加してハンター相手に120秒チェイスを決めて見事に4逃げ。他のメンバーにもよくやった助かったありがとうと言われれば気分も多少は上がる。水を飲むために食堂に向かう足もいつもより少し軽いようだった。
もうすぐ食堂に着くという所でそちら側から歩いてくる見知らぬ姿に気付く。ああ、彼が新しくやってきた人かと思う前にその様相に意識が持っていかれる。
痩せたその身を包む黒と白のボーダーの囚人服に重そうな首枷。僕も他人のことを言える姿ではないけれど、明らかに普通じゃない姿に思わず足が止まってしまった。そんな僕に向こうも気付いたらしく、こちらに向かって歩いてくる。距離が近付くにつれてはっきりと見えた顔には痛々しそうな青痣のついた左目が収まっていた。
緩く笑って何か、まず間違いなく挨拶の言葉だろうけれど。それを口にしようとした彼が前のめりに倒れ込み、え、と思うと同時に僕の腰に付いた磁石が浮いていることに気付く。そこからは一瞬だった。
「ぐえ、」
「うわ、」
ガキン、と硬質な物同士ががぶつかる音と潰れた声。少し視線を下に向ければ綺麗な旋毛が見える。瞬く間に起きた出来事に先程まで彼に抱いていたものがすべて吹き飛んでしまった。ぎこちなく首をこちらに向けた彼の瞳が元囚人という割には淀んでいなかったことを意外に思いはしたけれど、それよりなにより、
(なんだこいつ……)
という言葉が強く僕の頭に浮かんだ。そしておそらく向こうも同じことを思っていたのだろう。
そういう顔をしていた。
そんななんとも言えない初対面を果たしたルカ・バルサーという男は解読特化の優秀な男で重宝されているようだ。ようだと言うのは来て早々にゲームに駆り出されることが多くてまともに会話をしていないから彼がどんな人物であるかは人伝でしか知らないからだ。でもどうやらそれなりに良い人間であるようで、最初はどんな人間が来るのか不安そうだったウッズさんも今はにこやかに話している姿を見ることがある。
他にも新参の男3人で話していたり、発明が好きなもの同士でレズニックさんと真剣な顔で意見交換をしていたりしている所も見かけるけれど、そこに混ざろうなんて思わない。不必要な会話をしたくないし、別に彼に興味があるわけでもないからだ。
小腹が空いたので何かないかと食堂に向かう途中、そちら側から歩いてきていたウィリアムが僕に気付いて声をかけてきた。
「お、ノートン、明日のゲームの参加メンバーが貼り出してあったぜ」
「そうなんだ。僕も入ってた?」
「おう、お前とイライ、ナワーブ、ルカの4人だ」
「……ふーん」
救助1人、補助2人、解読1人というのはバランスの良い人選だ。時にはめちゃくちゃなメンバーを組まれたりするから今回は運がいい。バルサーさんと組むのは初めてだけど、レズニックさんとどう違うのかはよく知らない。でも、解読特化ならチェイスは期待出来ないだろう。
(最初に見つからないと良いけどね)
そんなことを思いながらウィリアムと別れて食堂に入るためにドアの取っ手に握る。けれど僕が力を入れる前に向こう側から勢いよく開かれた。突然のことに驚くと同時にドン、とぶつかってきた誰かの身体がそのまま倒れ込みそうなことに気付き、咄嗟に抱きとめる。視界に入った濃茶の1つに括られた髪でそれがバルサーさんであることが分かった。
「……っ、すまない、……っ!ぐっ……ぅ……!」
なんとか絞り出したのであろう謝罪を述べたかと思えば頭を押さえ呻く。どう見ても体調を崩しているその姿に、
「……大丈夫なんですか、明日」
と問いかけてからもう少し言い方はなかったのかと自分自身の発言に呆れる。
緩く上げられた顔は蒼白で額には脂汗、痛みで歪んだ瞳に引き結ばれた唇が彼の不調を分かりやすく表していたけれど、その唇を少しだけ綻ばせて彼はまた絞り出すように言葉を返してきた。
「大丈夫、迷惑は、かけない……」
そうして僕から離れ、壁を這うようにしながら歩いて行くバルサーさんの背を見送る。
不思議とその青白い顔が脳裏に焼き付いていた。
「やあ、今日はよろしく」
翌日、待合室に現れたバルサーさんは昨日の不調など無かったかのように僕たちに挨拶をした。僕の隣に座りクラークさんと談笑する姿を横目で見ていたらこちらを向いた彼と視線がぶつかり、何か言ったほうが良いだろうかと考えたところで彼の方から話しかけてきた。
「君と同じゲームに参加するのは初めてだな。よろしく」
「よろしくお願いします。……体調、大丈夫なんですか?」
「ああ、昨日はすまなかったな。今日は平気だ。足手まといにはならないように気を付けるが私はあまりチェイスが上手くないから、そっちは任せてしまいたいんだが……」
「まあ、ハンターに見つからないように気を付けてくださいね」
「善処するよ」
そこで彼との会話は終わった。
ガラスが割れるような音と共に視界に広がるのは何度も訪れた軍需工場だ。
とりあえず近くにあった暗号機の解読を始めて少しした頃にナワーブからハンターの接近を知らせるチャットが飛んできた。でもおそらくハンターは彼以外の標的を探すだろう。肘あてを5個持った健康状態のナワーブを追う利は薄い。
そしてどうやら予想通りだったようですぐに解読中というチャットが飛んできた。次に見つかるのは誰になるのかと解読をしながらも周りに気を配っているとこちらに向かってくるリッパーの姿が見えた。即座に暗号機から離れてチェイスのしやすい場所へ後ろに注意しながら走る。下手な動きをしたらその左手に纏う霧にやられてしまう。
ハンターの接近を知らせるチャットを打ちながら工場へ向かう。背後から放たれた霧を既の事で避け磁石で距離を取り、もう1つと放って工場の壁越しに引き付けスタンをかける。けれど向こうもそれを見越していた様子で遮蔽物を挟み、想定していたよりも随分と短い時間でこちらに迫ってきた。
(しまった……!)
窓に掛けた手に乗った体重を今更元には戻せない。大丈夫だと思ってクラークさんにフクロウを頼むチャットも送れておらず、常より大きく振りかぶられた凶刃に恐怖の一撃を覚悟した瞬間だった。
バチッという音とハンターの苛立ちを感じる声。痛みを伴うことなく越えられた窓を振り返れば忌々しそうに辺りを見渡し、結局は姿が見えている僕を追うことにしたのであろうリッパーが窓を越えているのを確認して、茂みに隠れる濃い茶髪とは逆方向へと駆けた。
その後、僕は捕まってしまったけれど想像していたよりずっと回っていたらしい暗号機は残り1台でしかも寸止めまで完了しているようで、こちらに向かって走ってくるナワーブと暗号機を上げる準備をしているクラークさん、ゲートの前で待機しているバルサーさんの姿が見える。リッパーが霧を放つ寸前に肘あてで距離を詰めて本体での攻撃を受けてから僕を救助。走り出してすぐに一撃受けた瞬間、通電の音が空気を震わせた。
「そのままゲートに向かえ!」
「でも、まだゲートが空いてないだろ?!」
「イライが開けてる!」
そんな馬鹿なとは思ったけれど言われた通りにゲートに向けて走る。後ろに僅かに視線をやれば僕の後ろを走るナワーブに向けて目を赤く光らせたリッパーが霧の刃を放ったところだった。
「なわ……」
「大丈夫だ前向いて走れ!」
霧がナワーブに届く寸前、鳥の高い鳴き声が聞こえ、そしてすぐに離れた。加速したリッパーがナワーブに一撃入れたけれど、健康状態のナワーブは引き留めるが付いた攻撃でも少しの時間耐えられる。そのままの勢いでゲートの向こうからこちらの様子を窺っていたクラークさんを通り過ぎて外へと出ていった。僕とクラークさんもその後に続く。4逃げ。完全勝利だった。
「お疲れさまでした。全員無事に脱出出来てなによりです」
「お疲れさん。フクロウ助かった」
「お疲れさまです。……バルサーさんは?」
「彼は逆ゲートから出たはずですからもう来ますよ」
クラークさんがそういうと同時に聞こえたドアの開く音にそちらを向けば、少し疲れた様子のバルサーさんがこちらへと歩いてきていた。
「バルサーさん、お疲れさまでした。ゲート開けの補助ありがとうございました」
「お疲れさま。役に立てたようで良かったよ」
そういえば彼は暗号機の解読やゲートの開放を別の場所にあるそれらから進めることが出来るのだった。なるほど、だからクラークさんがあんなに早くゲートを開けられたんだ。
「バルサーさん、ありがとうございました。ゲートも、工場での補助も。助かりました」
僕がそう言うと、
「迷惑、かけなかっただろ?」
と、彼は緩く笑いながら返してきた。
そんなやり取りから数日後。
僕は身体の奥底から湧き上がってくる苛立ちに蝕まれながら早足に廊下を歩いていた。前触れなく訪れるそれをうまく制御する術は未だ見つからず、自室で1人やり過ごすしかない。早く部屋に着け。誰にも会うな。誰も僕に話しかけるな。そう頭の片隅で祈るが、今日はそれが叶わなかった。
「あ、のーとんさ……」
僅かに俯かせていた顔を話しかけてきた彼女、ウッズさんに向ける。きっと恐ろしい顔をしていたのだろう、彼女は顔を強張らせた。その様子すら僕を苛立たせる。
そして、爆発した。
「お前も僕を頭がおかしい異常者だと思っているんだろう!?」
それからはもう言葉の暴力だった。自分でも何を言っているかはっきりとは分からず、けれど怯え俯くウッズさんの様子に止めなければという思いはあるのにそれを覆して余り有るほどの憎悪の熱が僕に口を閉ざさせてくれない。誰か止めてくれと願うが数少ないそれが出来る人が今この場にはいなかった。迷惑そうな者、無関心な者、心配しているが止めることは出来ない者。
ああ、なんてくそったれしかいない世界なんだ!
次の言葉を吐き出そうとした、その瞬間だった。
「女性をそんなに怒鳴るものじゃないぜ」
と言う声が聞こえたと同時に鋭い痺れが身体を走る。何事かと振り返るとそこにはやや呆れた様子のバルサーさんが立っていた。
「何があったのかは知らないが少し落ち着けよキャンベルさん」
「…………ぇ、ぁ、そう、ですね……」
曖昧な返事を返して気付いた。今しがたまで体内を荒れ狂っていた憎悪の熱が、まるで元々存在していなかったかのように落ち着いていることに。被害に遭ってしまったウッズさんも驚いているようだった。涙が滲む瞳を僅かに瞠っている。
「あの、ウッズさん、怒鳴ってすみません……」
「え、あ、大丈夫なの!お気になさらずなの!」
いつもは次の日になることが多い謝罪をするとウッズさんは大袈裟に感じるくらいのリアクションを返し、こちらに向かってきていたダイアーさんの所へと駆けていく。いつもと異なる流れにダイアーさんも驚いた様子でこちらを見ていたので軽く会釈をすると曖昧に笑みを返してくれた。
「君は案外感情の起伏が激しいんだな」
その声の方向に鈍く視線を向けると彼もこちらを見ていたので当然のように目が合ったけれどそれも一瞬のことで、バルサーさんはさっさと歩き去ってしまう。その背中をぼんやりと見送っているとゲームから帰ってきたナワーブ達に声を掛けられ、僕の意識はそちらへと向かいその日は終わった。
「君がこちらに来てくれないか?」
僅かな苛立ちを込めた声でそう言われ、すみません、と小さく謝る。
あの出来事を見ていた人達が広めたのだろう。僕が荒れていると誰かしらがバルサーさんを引っ張ってくるようになったのだ。発明で集中している時でもお構いなしに邪魔をされてしまっているらしく、その時は分かりやすく機嫌の悪そうな顔をしている。彼の放電と同程度の電気が流れる機械を作ったりもしていたけれど、何故か全く効果がなかった。それ故に彼の作業は邪魔され続け、我慢の限界を迎えて直訴しに来たようだ。
「迷惑かけてすみません。でも、本当に前触れが無くて……」
「ならいっそのこと私の近くにいてくれ。移動時間が無駄だ」
「良いんですか?それこそ邪魔になるんじゃ……」
「集中しているところを長く邪魔されるよりずっとマシだ」
そういうものなのだろうか。頭の作りが違う人間の考えはよく分からない。
あまり他人と一緒にいることは好きではないけれど、僕自身が自分に振り回されることにうんざりしていたから彼の厚意に甘えることにした。
「…………」
「…………」
カチャカチャと機械の部品と工具が奏でる小さな音に僕が本のページを捲る音が時折重なる。
あの日以来、僕がバルサーさんと一緒にいる時間は当たり前と言えばそうだけれど劇的に増えた。そうすると少しずつ会話も増え、彼のことも把握できるようになってくる。
何を言っても一切反応しない過集中状態と多少の反応はするが全てが曖昧な集中状態の見極めも今では慣れたものだ。そろそろ作業が一区切りする頃かと食堂に行きコーヒーを2つ持って戻ると、両腕を頭上で組み大きく伸びをする後姿が見えた。
「バルサーさん、コーヒー持ってきました」
「ああ、ありがとう」
彼の作業台とは別にある小さなテーブルにカップを置いて先程まで座っていた椅子に再び腰掛け一口コーヒーを啜る。この荘園で提供されている食事や飲み物は質が良いらしいけど、僕には違いがあまり分からない。
「君、あれから随分と落ち着いているんだな」
立ったままカップに口を付けるバルサーさんを見上げる。
そう、実はあの日から1度も僕の頭は荒れ狂っていない。一切の前触れなく訪れるその衝動の間隔なんて読めないけれど、こんなにも間が空くことはなかったはずだ。それに加えて普段から胸に燻っているはずの焦燥すら随分とおとなしくなっている。
「私は常に微量に放電しているようだから、もしかしたらそのあたりが影響しているのかもしれないな」
おそらく冗談だろう。軽く笑いながら言われたその言葉。でも、もしそれが本当だったらと考えて、
「それなら、僕はずっとあなたと一緒にいたいな」
なんて言ってしまった。なにを言っているんだと後悔しても出てしまったそれを無かったことには出来ない。
きょとん、と目を瞬かせたバルサーさんはすぐに噴出した。
「君、それじゃあまるでプロポーズだ」
そう言って笑う彼は普段より少し幼く見えて。僕の喉からまた勝手に言葉が出てきた。
「あの、」
「ん?」
「ルカって呼んでも良いかな?」
「唐突だな。別に好きに呼んでくれて良い」
「ありがとう。それで、もし、あなたが迷惑じゃなければ、僕のこと、ノートンと呼んでほしい」
「まあ、構わないが」
不思議そうな顔をした後、ふ、と微かに浮かんだ彼の笑みに、
見えないどこかが痺れた気がした。
そんな始まり。
弊荘園の探囚の始まり(かもしれない)