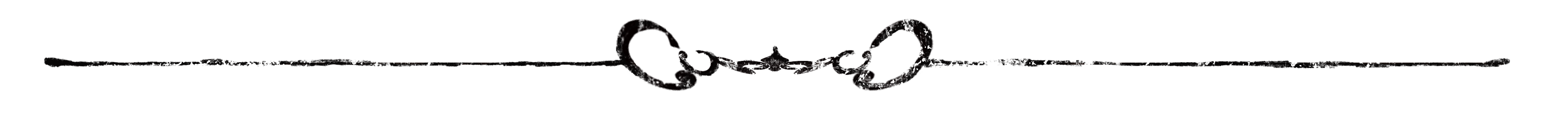首に熱を灯す。
ルカさんの首だけでイケるかなチャレンジの話。
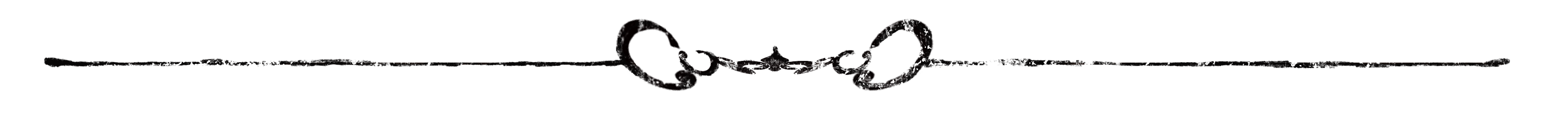
僕の恋人は首がとても弱い。
他の箇所は始めの方は鈍いくらい反応が悪かったくせに首への反応は抜群に良かった。
まあ、最初はお互いの欲を発散するためだけの行為だったからそこまで気にしていなかったけれど、なんやかんやあって今の関係になってからは積極的にあちらこちら開いている。とても楽しい。
「……っ、ぅ♡……っ!のーと、んっ、首やだ……ぁ♡」
「嘘つき。凄く締まってるよ」
後ろから覆い被さって腰を揺すると彼に挿入した僕の陰茎を包む熱い媚肉がきゅう、と収縮して思わず吐息が漏れた。それが首に当たったのか肩を跳ねさせ、僕の左手で押さえつけられている己の両手の自由を取り戻そうと力を籠めるのを強めに腰を打ち付けることによって阻む。
ルカは情事の際に声を殺そうとするからこうやって両手の自由を奪ってやることが多い。何故なら僕は声を聴きたいからだ。恋人の可愛い啼き声を聴きたいと思うのは至極当然のことだと思う。
「ルカは本当に首が弱いね」
「っ♡、分かっているな、ら、♡、やめてくれ、ないか……!ひ、ぅ♡」
悪態をつこうとするルカの首筋を強めに吸えば肩を跳ねさせ、なんとか動かせる指先でシーツを手繰り寄せ、額をシーツに擦りつけて快楽に耐えようとしているようだった。
こんなに弱くてよく普段首枷を付けていられるな。と感心していると、ふと邪な考えが浮かぶ。
もしかしたら首への刺激だけで彼は達することが出来るのはないか。と。
「ぁ……?ぅ、のー、とん?、ぅ♡」
「なんだい?」
腰の律動を止め、より強く彼の身体を押さえ込む。そうすると戸惑ったように名前を呼ばれる。それに努めて平静に返すと戸惑った様子でこちらに顔を向けてきた。
「な、んで……?」
「なにが?」
「……ぅ、なんで、とめ、……」
「うん、ちょっと試したいことがあって」
「…………?」
困惑しているルカの耳に注ぎ込むように囁く。
「あなたが首だけでイケるのか」
その言葉にさぁ、と顔を青ざめさせる彼に前を向かせ、項を殊更ゆっくりと舐め上げれば引き攣った声を上げながらいやいやと頭を振って逃げようとするけれど、身体を押さえ込まれているので大した意味はなかった。
「やだぁ、!む、無理だ……っ!むり……ぃ!ぅう♡」
「大丈夫、ルカなら出来るよ」
状況が違えばとても良い言葉なのに今この場ではとても酷い言葉だ。
赤く染まった首筋を柔く噛むと僕の身体の下の痩身が気持ちいいくらい大袈裟に跳ねる。
「頑張ろうね、ルカ」
そう告げる僕はきっと意地の悪い顔をしているだろう。
「ぁ、ぁ~……っ!♡、ひ、ぃっ♡、やめ、のーとん、っ♡、う゛、ぅ゛っ!やだ、やだぁ…!、♡♡♡」
「こら、駄目だよ腰を動かしたら」
首への愛撫を続けていると、決定的な刺激を求めて自ら腰を振ろうとするから腕を回すことでそれを阻む。
僕だって動くのを我慢しているのだからルカにも我慢してもらわないと。
舌を這わせ、吸い、緩く噛んで薄くついた歯型を舐め上げる。
我慢できなくなってきたのだろう水気の増えた喘ぎが耳に心地よかった。
しばらくそうしていると腰に回した腕に伝わってきていた彼の腹の痙攣がひく、と一瞬止まり、
「ぁ……?♡ぅ゛……!?……ッ゛!♡」
小刻みだったルカの身体の震えが大きくなる。
首を舐める度、吸う度、どんどんと酷くなっていく。
「は、はなし゛て゛ぇ゛っ!♡♡くひ゛ぃ、やた゛……ぁッ!♡」
流石になりふり構わずに力を入れられると抑え込むのが大変だ。けどもうすぐ見たいものが見えるという確信があった。
「ぁ゛、ぁっ、ぅう゛!♡♡、イ゛ッ、ぅ゛……ぅ゛っ!」
最後の仕上げに首筋に少し強めに噛み付けば一際大きく痩身が震えて、
「ぅ゛、~~~~~~~~~っ!♡♡♡」
搾り取るようにうねった媚肉に思わず息を詰める。
痙攣するルカの下腹部を撫でて気付く。精液を吐き出した痕跡がない。
ドライオーガズムで絶頂したんだ。
ぞく、と背筋に甘い痺れが走る。おかしいな、僕に加虐趣味はなかったはずなんだけどな。
震える彼の片足を掴んで挿入したまま向かい合う形に体位を変え、噛み付くようにキスをする。半開きになっていた唇の中に舌をねじ込み歯列をなぞり力の抜けている舌と絡め、唾液を交換するような繋がりを求めると飲み込み切れなかった唾液がルカの口の端から溢れ、顎を伝ってシーツに垂れていった。
「ん゛ぅ、ん゛♡、ぅ゛♡、」
唇を離せば透明の糸が引き、ぷつり、と切れる。
そしてずっとお預け状態になっていた腰を勢いよく打ち付ければもはや声を殺す余裕などまるでないルカは気持ちいいくらい素直に啼いてくれた。
「君は酷い奴だ」
シーツから顔だけ出したルカがこちらを睨みつけながら悪態をつく。
いつもより掠れた声が可愛くて笑えば何がおかしいとばかりに眼光が鋭くなった。
「だってルカはいつも声を出すのを我慢するだろう?たまには恋人の可愛い声を聴きたくて。あとはまあ、好奇心で」
「……っ、」
"恋人”という言葉にルカは弱い。むずがゆそうな表情を受けべて顔を逸らす彼の赤くなった首を見れば転々と付いた赤い跡が目に入って僕の機嫌は良くなるばかりだ。
「たまにしかしないからさ。許してくれる?」
そう言いながらその首筋を撫でようと手を伸ばせば、
「許さない」
「い゛っ!!!」
バチッ、という音と共に痛みと痺れに襲われた。